
����́ADomain Name Service�ɂ��Ċw�т܂��傤�B
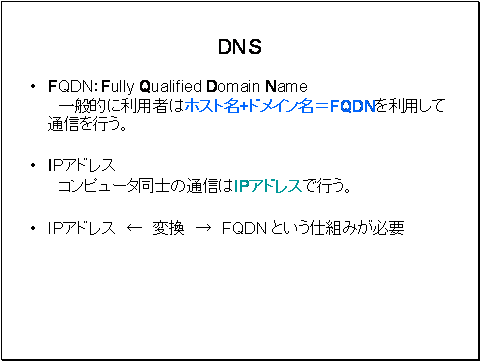
��ʓI�ɗ��p�҂��z�X�g��+�h���C��������Ȃ�FQDN�𗘗p���ĒʐM���s���܂��B
����ɑ��A�R���s���[�^���m�̒ʐM��IP�A�h���X�ōs���܂��B
�����ŁAFQDN ��IP�A�h���X�ɁAIP�A�h���X��FQDN�Ɂ@�ϊ�����Ƃ����d�g�݂��K�v�ƂȂ�܂��B
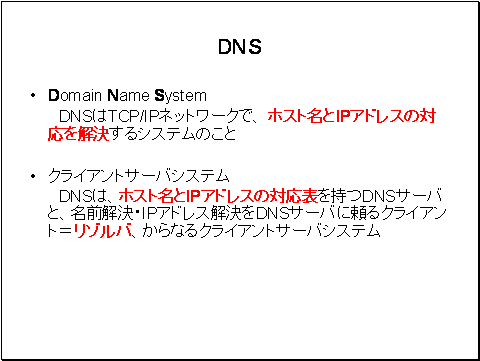
���́AFQDN ��IP�A�h���X�ɕϊ�����A�t�ɁAIP�A�h���X��FQDN�ɕϊ�����A�Ƃ�����ڂ�Domain Name Service�@DNS���S���Ă��܂��B
TCP/IP�l�b�g���[�N�ŁA �z�X�g����IP�A�h���X�̑Ή�����������ꍇ�Ɂ@DNS�͕K�v�ȃV�X�e���ƂȂ��Ă��܂��B
DNS�́A
�z�X�g����IP�A�h���X�̑Ή��\������DNS�T�[�o�ƁA
���O�����EIP�A�h���X������DNS�T�[�o�ɗ���N���C�A���g�����]���o�A
����Ȃ�N���C�A���g�T�[�o�V�X�e���ł��B
DNS�T�[�o�̕ێ����Ă����z�X�g����IP�A�h���X�̑Ή��\�͈��̃f�[�^�x�[�X�ł��B�����z�X�g����IP�A�h���X�̑Ή��\���i�[���Ă���t�@�C�����]�[���t�@�C���ƌĂт܂��B
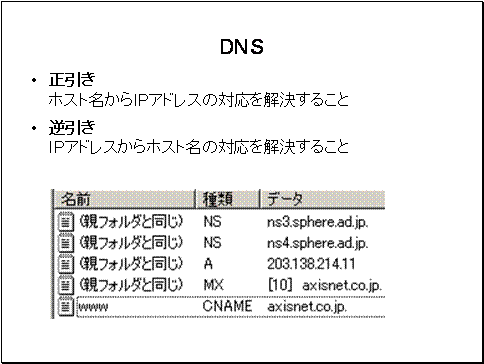
�z�X�g������IP�A�h���X�̑Ή����������邱�Ƃ��������ƌ����܂��B
IP�A�h���X����z�X�g���̑Ή����������邱�Ƃ��t�����ƌ����܂��B
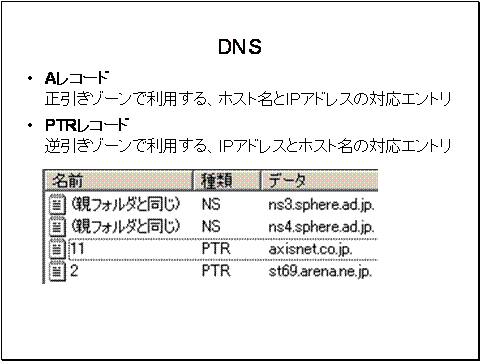
�������]�[���ŗ��p����A�z�X�g����IP�A�h���X�̑Ή��G���g����A���R�[�h�ƌ����܂��B
�t�����]�[���ŗ��p����AIP�A�h���X�ƃz�X�g���̑Ή��G���g��PTR���R�[�h�Ƃ����܂��B
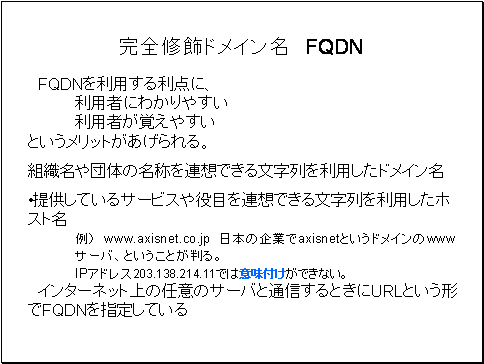
��قǐ��������悤���z�X�g��+�h���C��������Ȃ镶�����FQDN�ƌĂт܂��BFQDN�𗘗p���闘�_�ɁA
���p�҂ɂ킩��₷��
���p�҂��o���₷��
�Ƃ��������b�g���������܂��B
�g�D����c�̖̂��̂�A�z�ł��镶������h���C�����Ƃ��ė��p�ł��܂����A
���Ă���T�[�r�X���ڂ�A�z�ł��镶������z�X�g���Ƃ��ė��p�ł��܂��B
�Ⴆ�@www.axisnet.co.jp �Ƃ���������̏ꍇ�A����IP�z�X�g��ݒu�����G���W�j�A�łȂ��Ă��A�@���{�̊�ƂŇAaxisnet�Ƃ����h���C���̇Bwww�T�[�o�ł���A�Ƃ������Ƃ�����܂��B
���݁A���̃z�X�g������IP�A�h���X203.138.214.11�ł͂��̂悤�ȕ֗����Ӗ��t�����ł��܂���B
�������͓���A�C���^�[�l�b�g��̔C�ӂ̃T�[�o�ƒʐM����Ƃ���URL�Ƃ����`��FQDN���w�肵�Ă��܂��B
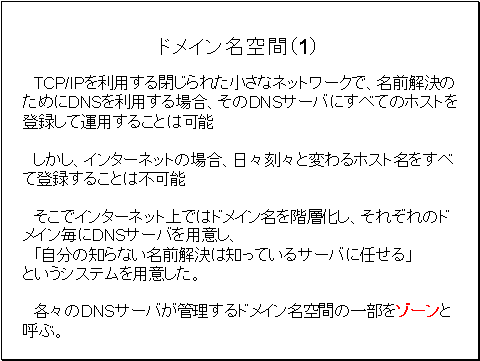
�@TCP/IP�𗘗p�������ꂽ�����ȃl�b�g���[�N�ŁA���O�����̂��߂�DNS�𗘗p����ꍇ�A����DNS�T�[�o�ɂ��ׂẴz�X�g��o�^���ĉ^�p���邱�Ƃ͉\�ł��B
�@�������A�C���^�[�l�b�g�̏ꍇ�A�T�[�o�Ɍ��肵�Ă��A���X���X�ƕς��z�X�g�������ׂēo�^���邱�Ƃ͕s�\�ł��B
�@�����ŃC���^�[�l�b�g��ł̓h���C�������K�w�����A���ꂼ��̃h���C������DNS�T�[�o��p�ӂ��A
�@�u�����̒m��Ȃ����O�����͒m���Ă���T�[�o�ɔC����v
�Ƃ����V�X�e����p�ӂ��܂����B
�@�e�X��DNS�T�[�o���Ǘ�����h���C������Ԃ̈ꕔ���]�[���ƌĂт܂��B�e�X��DNS�T�[�o�͎����̊Ǘ����Ă���h���C�����z�X�g����IP�A�h���X�̑Ή��\��ێ����܂��B�����z�X�g����IP�A�h���X�̑Ή��\���i�[���Ă���t�@�C�����]�[���t�@�C���ƌĂт܂��B
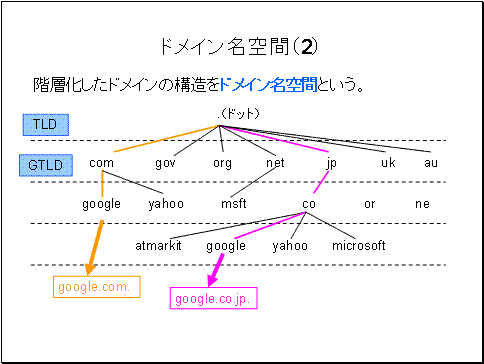
�K�w�������h���C���̍\�����h���C������� Domain Name Space�ƌĂт܂��B
�h���C������Ԃ̊K�w�\���͂����̐}�̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B
uk��au�h���C���̉����ɂ�jp�h���C���Ɠ��l�ɁAco�Ene�Eor�Ego�Ȃǂ̃T�u�h���C��������܂��B
co�Ene�Eor�Ego��com�Enet�Eorg�Egov�̉����ɂ͒c�̂��ƂȂǑg�D�̃h���C�����T�u�h���C���Ƃ��đ��݂��܂��B
�Ǘ����Ă���g�D�������Ƃ������Ƃ͑��X����܂����A�c���[�\���̎}�ʂꂽ��Ŏ}���Ăэ������邱�Ƃ͂���܂���B���̎}�\���i�c���[�\���j�ɂ���ă��j�[�N�ȃh���C��������ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B
�Ⴆ�Awww.google.com��www.google.co.jp�͂������www�Ƃ����z�X�g����google�Ƃ����h���C����������ł����A��ʃh���C����com��co.jp�ƈقȂ邱�ƂŁA�ʂȃh���C���ɑ�����z�X�g�Ƃ��ċ�ʉ\�ɂȂ�܂��B
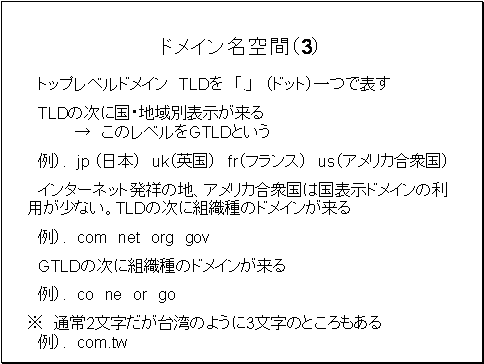
�h���C��������̍\���E�K���Ƃ��ăg�b�v���x���h���C���@TLD���ǂ��ƈ�ŕ\���܂��BUnix�݊�OS��root���X���b�V��1�ŕ\���̂Ɏ��Ă��܂��ˁB
Web�u���E�U��URL����͂��鎞�ɂ́AFQDN�Ƃ��ē��͂��镶����̍Ō�ɂ��̃h�b�g�̓��͂͏ȗ��\�ł��B�ꕔ��DNS�T�[�o�A�v���P�[�V������nslookup�R�}���h�ł͏ȗ��ł��Ȃ����Ƃ�����܂��B
TLD�̎��ɍ��E�n��ʕ\���̃h���C�������܂��B���̃��x����Generic Top Level Domain GTLD�Ƃ����܂��B���{��.jp�A�p����uk�A�t�����X��fr�A�A�����J���O����us�ł��B
�������A�C���^�[�l�b�g���˂̒n�ł����A�����J���O���͍��͂܂����\���̃h���C��us�̗��p�����܂肠��܂���BTLD�̎���com�@net�@org�@gov�Ƃ������g�D��̃h���C�������܂��B�����Ƃ̃h���C���Ǘ����s����ȑO�͂��̕��@�ł����B
gTLD�̎���co�@ne�@or�@go�g�D��̃h���C�������܂��B�g�D��̃h���C���͒ʏ�2�����ł����A�A�����J���O�����p�̂悤��3�����̂Ƃ��������܂��B
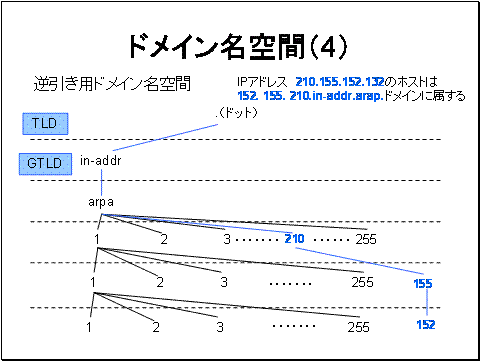
�h���C������Ԃɂ�IP�A�h���X����FQDN����������A�t�����p�̃h���C�����p�ӂ��Ă���܂��B
IPv4�A�h���X�́A32�r�b�g���I�N�e�b�g�ƌĂ�8�r�b�g�Â�4�u���b�N�ɕ������ĕ\�L���Ă��܂��B�����ŁA�ő�6�K�w�Ńz�X�g�̑�����h���C�������ł��܂��B
IP�A�h���X�@210.155.152.132�̃z�X�g��152. 155. 210.in-addr.arap.�h���C���ɂȂ�܂��B
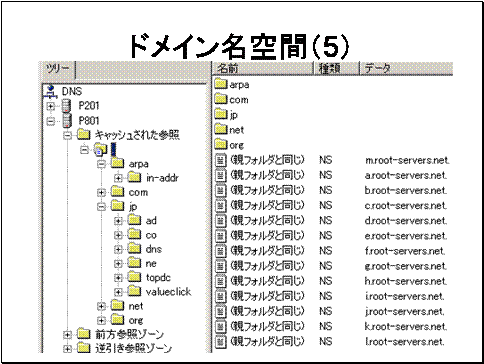
���ۂ�LAN�Ŏg�p������DNS�T�[�o�Ńh���C������Ԃ̊K�w�\�����m�F�ł��܂��B
DNS�T�[�o�͊Ǘ����Ă���l�b�g�[�N��̃N���C�A���g�z�X�g����A�C���^�[�l�b�g��Ȃǎ��g���Ǘ����Ă��Ȃ��l�b�g���[�N��̃z�X�g��ΏۂƂ��閼�O�����̃��N�G�X�g�̖��O�����ɐ�������ƁA��莞�ԃL���b�V���Ƃ��Đ����G���g����ێ����܂��B���̉����L���b�V���͂��������t�@�C���̃f�B���N�g���Ɠ��l�Ƀc���[�ƍ\���Ƃ��Ċm�F�ł��܂��B
�g�b�v���x���h���C����\���h�b�g�̊K�w��I������ƁA�g�b�v���x���h���C�����Ǘ����Ă��鐢�E��13���DNS�T�[�o�̃G���g�����m�F�ł��܂��B���̃g�b�v���x���h���C�����Ǘ����Ă���DNS�T�[�o��root�T�[�o�Ƃ����܂��B
root�T�[�o�̓g�b�v���x���h���C���̏��݂̂������܂��BgTLD�Ȃlj��̊K�w�̏��͂��̃h���C���̃T�[�o�ɈϔC���܂��B���l�ɍX�ɉ��̊K�w�ł��ϔC���s���Ă��܂��B
�@��1�@root�T�[�o��jp�h���C���̏���jp�h���C�����Ǘ����Ă���T�[�o�ɈϔC����
�@��2�@jp�T�[�o��co�h���C���̏���co�h���C�����Ǘ����Ă���T�[�o�ɈϔC����
DNS�T�[�o�ɂ�閼�O�����͈�������͐���̃T�[�o�ŃC���^�[�l�b�g��̑S�Ẵz�X�g����IP�A�h���X�̑Ή����Ǘ����Ă���̂ł͂Ȃ��A���̗l�Ƀh���C�����x���Ɗe�h���C���ŕ��U���ĊǗ����Ă��܂��B
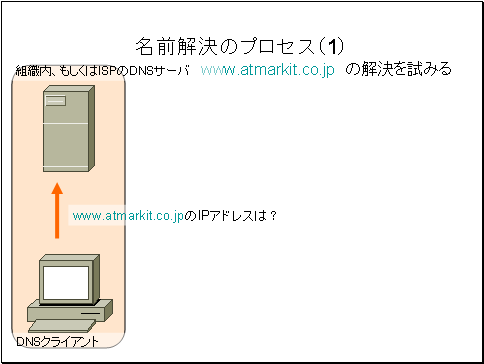
�ł͋�̓I�ɕ��U�Ǘ��̃v���Z�X�����Ă����܂��傤�B
��Ƒg�D�A�������́A�ƒ��PC��www.atmarkit.co.jp��web�y�[�W�ɃA�N�Z�X���鎖��z�肵�܂��B
���[�U�[�����삵�Ă���PC��www.atmarkit.co.jp�Ƃ����z�X�g��IP�A�h���X���A���[�U�g�D����DNS�T�[�o�A�������͉������Ă���ISP��DNS�T�[�o�ɖ₢���킹�܂��B
Windows PC�̏ꍇ�Aipconfig /all�R�}���h�Ŗ₢���킹���DNS�T�[�o��IP�A�h���X���m�F�ł��܂��B
�܂��A���̖₢���킹�Ƃ���������N�G���Ƃ������܂��B
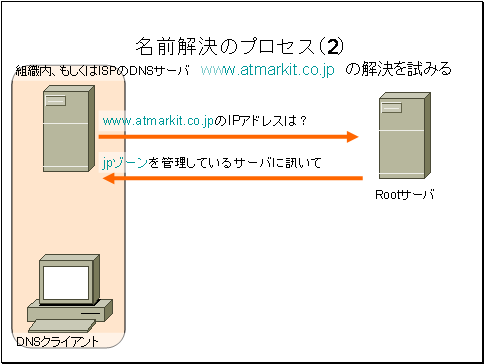
���[�U�g�D����DNS�T�[�o�A�������͉������Ă���ISP��DNS�T�[�o�́Aroot�T�[�o�ɑ���www.atmarkit.co.jp��IP�A�h���X��₢���킹�܂��B
Root�T�[�o�̓N�G�������߂��āAjp�h���C���ijp�]�[���j���Ǘ����Ă���DNS�T�[�o�ɃN�G������悤��jp�h���C���ijp�]�[���j���Ǘ����Ă���DNS�T�[�o�̃A�h���X��Ԃ��܂��B
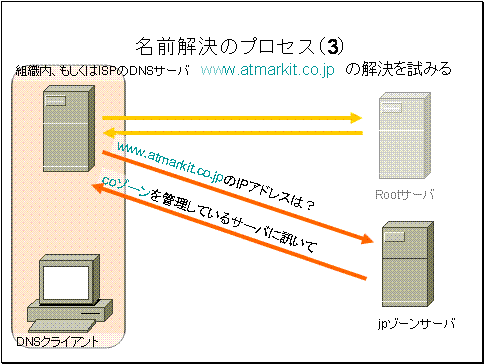
�����Ń��[�U�g�D����DNS�T�[�o�A��������ISP��DNS�T�[�o�́Ajp�\�[����DNS�T�[�o��www.atmarkit.co.jp��IP�A�h���X��₢���킹�܂��B
Jp�\�[���T�[�o�̓N�G�������߂��āAco.jp�h���C���ico.jp�]�[���j���Ǘ����Ă���DNS�T�[�o�ɃN�G������悤��co.jp�h���C���ico.jp�]�[���j���Ǘ����Ă���DNS�T�[�o�̃A�h���X��Ԃ��܂��B
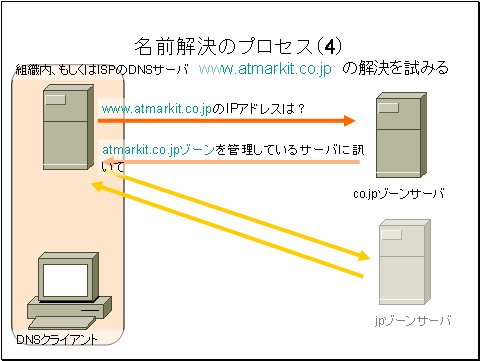
�����Ń��[�U�g�D����DNS�T�[�o�A��������ISP��DNS�T�[�o�́Aco.jp�\�[����DNS�T�[�o��www.atmarkit.co.jp��IP�A�h���X��₢���킹�܂��B
co.jp�\�[���T�[�o�̓N�G�������߂��āAatmarkit.co.jp�h���C���iatmarkit.co.jp�]�[���j���Ǘ����Ă���DNS�T�[�o�ɃN�G������悤��atmarkit.co.jp�h���C���iatmarkit.co.jp�]�[���j���Ǘ����Ă���DNS�T�[�o�̃A�h���X��Ԃ��܂��B
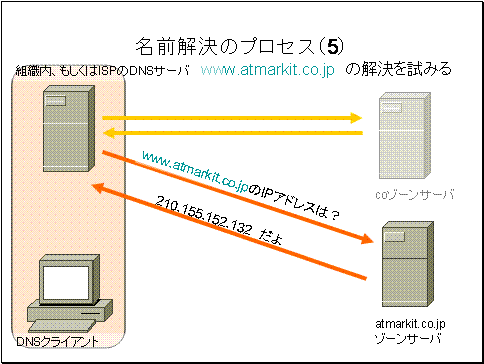
�����Ń��[�U�g�D����DNS�T�[�o�A��������ISP��DNS�T�[�o�́Aatmarkit.co.jp�\�[����DNS�T�[�o��www.atmarkit.co.jp��IP�A�h���X��₢���킹�܂��B
atmarkit.co.jp�\�[���T�[�o�̓N�G�������߂��āAwww.atmarkit.co.jp��IP�A�h���X��Ԃ��܂��B
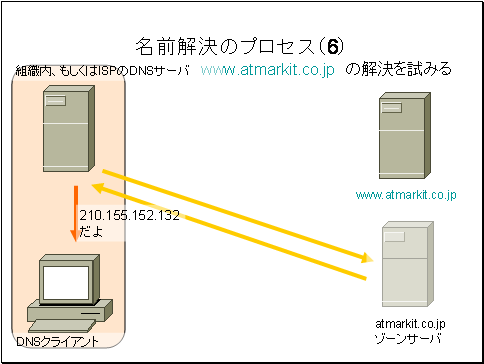
���[�U�g�D����DNS�T�[�o�A��������ISP��DNS�T�[�o�́A���̂�www.atmarkit.co.jp��IP�A�h���X��₢���킹���̃N���C�A���g�ɕԂ��܂��B
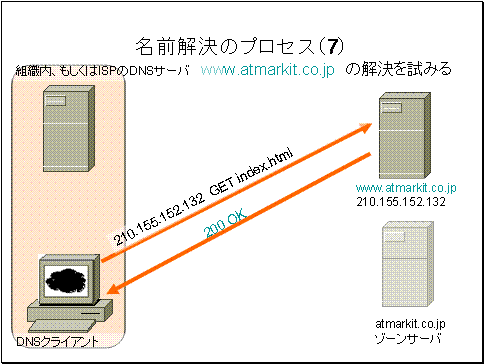
�N���C�A���gPC�͉Ƃ��ē���IP�A�h���X���g�p����www.atmarkit.co.jp�ƒʐM���܂��B
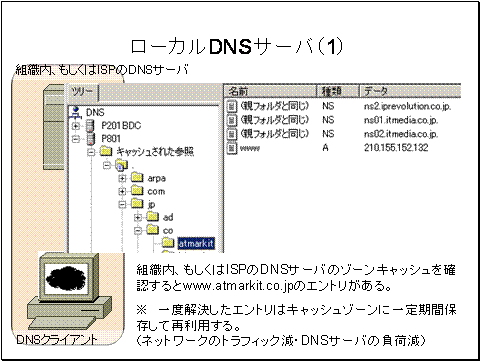
�N���C�A���gPC���璼�ڃN�G�����郆�[�U�g�D���E��������ISP��DNS�T�[�o�����[�J��DNS�T�[�o�ƌĂԎ����L��܂��B
���[�J��DNS�T�[�o�͎������Ǘ����Ă���]�[���̏����Ǘ����Ă���̂͂������ł����A�O���̃T�[�o�ʼn��������N�G�����ʂ���莞�ԃL���b�V���Ƃ��ĕێ����܂��B
�L���b�V���Ƃ��ĕێ����Ă���ԂɍĂуN���C�A���gPC����N�G������ƁA���̎��͊O���T�[�o�փN�G���𑗐M�����ɃL���b�V�����𗘗p���ĉ��܂��B�l�b�g���[�N�̃g���t�B�b�N���E�O����DNS�T�[�o�ɑ��镉���Ƃ��������b�g������܂��B����13��݂̂ʼnғ����Ă���root�T�[�o�͑S�C���^�[�l�b�g�̃N�G������������̂ŕ��ׂ������B
�f�����b�g�Ƃ��āA�L���b�V����ێ����Ă���ԂɑΏۂ̃z�X�g��IP�A�h���X�ύX���Ă��܂��ƁA���̃z�X�g�ւ̃A�N�Z�X�Ɏ��s���Ă��܂���������܂��B
���ӂ��������T�[�o�֗U�����邽�߂�DNS�L���b�V���ɕs���ȃN�G�����ʁi���K��IP�A�h���X�ł͂Ȃ�IP�A�h���X�j�𑗂荞��DNS�|�C�Y���L���b�V���Ƃ����U�����@�����邱�Ƃ��o���Ă����܂��傤�B
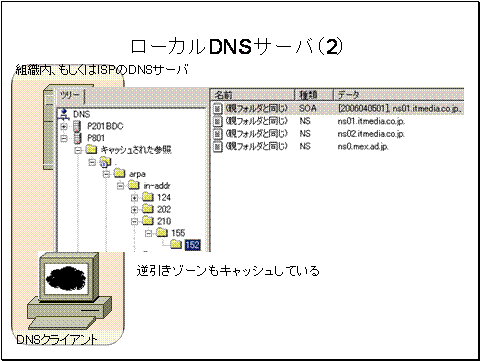
IP�A�h���X����z�X�g������������t�������L���b�V�����Ă���̂��m�F�ł��܂��B
�������]�[���L���b�V���Ƌt�����]�[���L���b�V����DNS���O��Ԃ��h�b�g���\�����[�g���N�_�Ƃ����K�w�\���ɂȂ��Ă��鎖���킩��܂��B
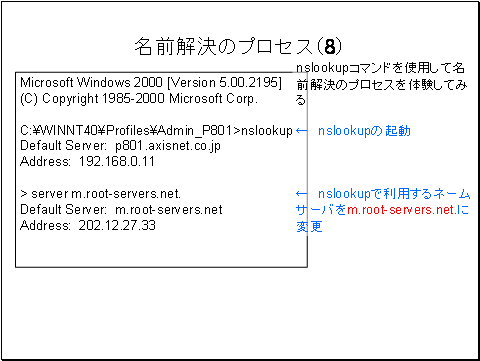
nslookup�R�}���h�𗘗p����Ɩ��O�����̃v���Z�X���̌��ł��܂��B�i���ۂɂ͖��O�����ł͂Ȃ�DNS�T�[�o�̎����̌����ƂȂ�܂��B�j
������������nslookup�R�}���h���N�����܂��Bnslookup�̃V�F���Ńv�����v�g�\���ɂȂ�܂��B
server�R�}���h�ŏ���ɗ��p����T�[�o��root�T�[�o�ɐݒ肵�܂��B��ɐ��������悤�Ƀ��[�g�T�[�o��13�䑶�݂��܂��B�ǂ�ɐݒ肵�Ă����܂��܂���B��ł�m.root-servers.net�ɂ��Ă��܂��B
���[�g�T�[�o��net�h���C�����Ǘ�����root-servers.net�Ƃ����h���C���̃z�X�g�ł��B���܂Ő������Ă������ȏ��I�����ł�
�܂����[�g�T�[�o�ɃN�G�����o��
����net�h���C���̃T�[�o�ɃN�G�����o��
����root-servers.net�h���C���̃T�[�o�ɃN�G�����o��
�ƂȂ�܂����A����ł́u���[�g�T�[�o�̖��O�����Ƀ��[�g�T�[�o�𗘗p����v�Ƃ��������������܂��B�����ň�ʓI��DNS�T�[�o�A�v���P�[�V�����ɂ̓��[�g�T�[�o�̂݃��[�J���Ŗ��O�����ł���悤�ɁA13��̃��[�g�T�[�o�̃z�X�g����IP�A�h���X�̏����͂��߂���p�ӂ��Ă��܂��B
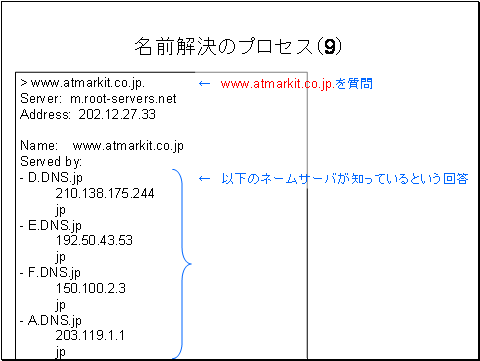
www.atmarkit.co.jp�Ƃ����z�X�g���̕��������͂���ƁADNS�T�[�o�̎����̒�����Ή�������\������܂��B
����́A
������DNS�T�[�o��www.atmarkit.co.jp�̖��O�������o����
�Ƃ�����������܂����B
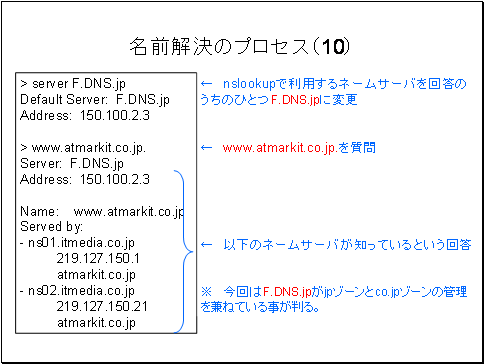
����ꂽ�̒�����ЂƂ̃T�[�o��I���server�R�}���h�ŏ���ɗ��p����T�[�o��ݒ肵�܂��B
���Ƀz�X�g��www.atmarkit.co.jp���N�G�����܂��B
������A
������DNS�T�[�o��www.atmarkit.co.jp�̖��O�������o����
�Ƃ�����������܂��B
�܂��Aatmarkit.co.jp���Ǘ����Ă���DNS�T�[�o�����Ă������Ƃ���F.DNS.jp��jp�]�[����co.jp�]�[���̊Ǘ������˂Ă��鎖������܂��B
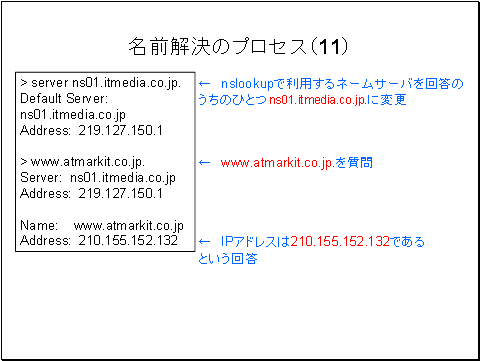
����ꂽ�̒�����ЂƂ̃T�[�o��I���server�R�}���h�ŏ���ɗ��p����T�[�o��ݒ肵�܂��B
���Ƀz�X�g��www.atmarkit.co.jp���N�G�����܂��B
IP�A�h���X���Ԃ���܂����B
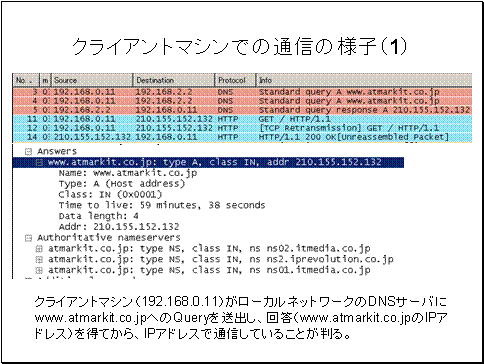
�N���C�A���g�}�V����Etheral�Ȃǂ̃v���g�R���A�i���C�U���N�����A�g���t�B�b�N���L���v�`������ƁA
���[�J��DNS�T�[�o�ɖ��O�����N�G���𑗐M��
�Ή�����IP�A�h���X�Ă���
IP�A�h���X���m�ŒʐM���Ă���
��������܂��B
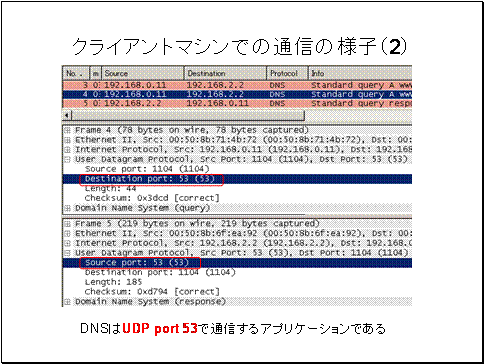
�܂����O�����N�G���ƃN�G�����ʁi���X�|���X�j�̃p�P�b�g������ƁADNS�T�[�o��UDP�|�[�g53�Ԃ𗘗p���Ă��鎖���킩��܂��B
DNS�̓T�[�o����UDP��53�ԃ|�[�g���g�p���A�N���C�A���g����UDP�̃����_���|�[�g�����g�p����application�Ƃ������Ƃ�����܂��B
UDP�͍đ���G���[����Ƃ����d�g�݂������Ȃ��M�����̖����v���g�R���ł��B���ʃI�[�o�[�w�b�h�����Ȃ��ʐM��ł��܂��BDNS�͖��O�����Ƃ�����ڂ���g�̂��Ȃ��̌y���v���g�R���Ŏ�������܂����B
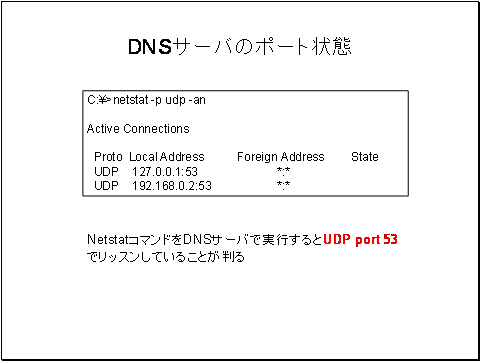
DNS�T�[�o���netstat�R�}���h�����s�����UDP�|�[�g53�ԂŃ��b�X���i�҂��j���Ă���l�q���킩��܂��B
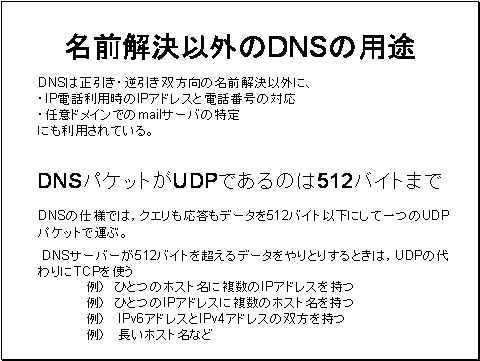
DNS�T�[�o�͖��O�����ȊO�ɂ��A
�EIP�d�b���p����IP�A�h���X�Ɠd�b�ԍ��̑Ή�
�E�C�Ӄh���C���ł�mail�T�[�o�̓���
�̖�ڂł����p����Ă��܂��B
�{�u���Ŋ��ɁADNS�p�P�b�g��UDP�ł���A�Ƃ������Ƃ��w��ł��܂����A������TCP��DNS�p�P�b�g�ɂ��ĐG��Ă����܂��B
DNS�̎d�l�ł́C�N�G�����������f�[�^��512�o�C�g�ȉ��ɂ��Ĉ��UDP�p�P�b�g�ʼn^�т܂��B������
�ЂƂ̃z�X�g���ɕ�����IP�A�h���X�����ꍇ��
�ЂƂ�IP�A�h���X�ɕ����̃z�X�g�������ꍇ
IPv6�A�h���X��IPv4�A�h���X�̑o�������ꍇ
�����z�X�g���̏ꍇ
�ɁADNS�T�[�o�[��512�o�C�g����f�[�^�����Ƃ肷�邱�Ƃ�����܂��B���̂悤�ȂƂ��́CUDP�̑����TCP���g��512�o�C�g����f�[�^�������܂��B